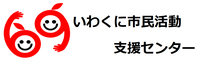「防災からまちづくりへ」~住民のつながりを更に強く・太く~
日 時:令和2年2月17日(月)19:00~20:30
場 所:愛宕供用会館 集会室
講 師:幸坂 美彦氏(一般社団法人 いのちを守る防災危機管理協会代表)
参加者:49名
●あいさつ
愛宕地区自主防災組合連合会会長 牛尾氏
●講師紹介
一般社団法人 いのちを守る防災危機管理協会代表 幸坂氏
防災士、防災アドバイザー、山口市社会教育委員など防災協会専任講師として活動を展開。
●講座
これまでに実施したまち歩きやアンケート結果に基づいてまとめた防災マップが確定し、防災まちづくり計画の将来ビジョンを検討中。
〇ふりかえり
・愛宕地区自主防災組織連合会の設立
・自主防災担当者が集まり学習会を実施
・住民参加の防災講演会
・愛宕地区をまち歩き(危険個所の確認/昔の歴史を伝承)
・アンケートの実施
・リーダーの養成
・「わが家のひなんマップ」の作成(自治会長が説明しながら年度末全戸配布予定)
→担い手づくり(若い世代・小中学生を養成)
〇地域課題
・自主防災組織の存在を知らない 49%
・防災への関心あり 9割
・防災活動に参加したい 7割
・避難意識はあるものの実際の避難は 3%、防災対策をしている 3割
・過去の被災履歴を知らない 4割
・災害時に頼りにするのは 家族3割、近所2割
・災害時に必要 ①避難誘導 ②情報網整備 ③防災意識の啓発
↓
「災害から命を守る」
自助:自分の命は自分で守る、自分でできる事は自分で
共助:学校や地域で守る ⇒ 地域防災力(自治会に意識付けする)
公助:公的機関の支援
〇自治会での組織づくり
・連絡網の整備や情報伝達訓練の実施
・防災教室、防災グッズの展示など(体験することが大事)
・単位自治会→地区→愛宕全体での訓練
〇これから~地域へ浸透中、何が必要か~
・継続した活動
・役員だけでなく住民も取り込んだ活動を
「いわくに消防防災センター」へ実際に行ってみる(本日参加者9割が見学済み)
→人と人とのつながりが大切
〇まとめ
①単位自治会から愛宕3地区への取り組み
②できるできないでなく、やってみる
③リーダーシップと人のつながりが必要
人の命をどうやって守っていくか→住民を巻き込んで、新しい愛宕のまちづくりへ
※年度末までに愛宕地区防災まちづくり計画の将来ビジョンの確定
●アンケート結果
〇参加地区
牛野谷 8 尾津 6 門前 16 横山 2 玖珂 1 川下 1
〇性別
男性 60代 9 70代 18 80代 1
女性 40代 1 60代 2 70代 2
不明1
〇今回の研修内容の感想は?
非常に参考になった 22
参考になった 11
あまり参考にならなかった 0
無回答 1
〇単位自治会で防災意識の共有はできているか?
共有している 9
共有していない 15
わからない 10
〇もしもの時何が必要?
飲食料、コミュニティ、情報、避難経路、避難場所、他
〇もしもの時どうしたらいい?
いのちを守る、近所への呼びかけ、避難マップの把握、情報の入手、高齢者への支援、他
〇防災マップを家族で共有しているか?
共有している 15
共有していない 17
何もしない 1
その他 1
〇単位自治会で連絡網の整備をしているか?
整備している 6
整備していない 25
その他 1
無回答 2
〇防災訓練は必要か?
必要 33
必要ない 1
その他 0
〇必要と思われる方はどの地域でどのようにするのがいいか?
各々の自主防災組織で隔年で場所を変えて行い、その隔年間に総合的な訓練を行う。
近助は必要なので単位自治会が連絡を取り合う。
どのような対処をしていいかわからない。
リーダーを作る。
自分の近くに何の災害があるか研究、訓練する。
全地域で一斉に。
日頃から訓練しておく。
各自治会ごとに訓練し、地区ごとに総合的に訓練する。
高齢者等はもちろんだが、小中学校も含めて訓練する。
単位自治会で連絡網の確認。
働き盛り世代が参加できる方法、区切りで。
自治会単位での防災学習と避難訓練をする。
住んでいる地域で元気な人が高齢者等を手助けできる人材を多く決めていく。
各エリアごとに、指示のみで向く行動を伴う訓練。
近接自治会と一緒に。
定期的な実地。
高齢者を連れての移動手段や移動方法、自助の限界がある。
〇必要ないと思われる方はその理由は?
各自の状況により行動を決めればよい。
訓練の内容によるが、避難については各自の判断をしっかり身に付ける。
〇その他の意見
家族や自治会の方々には災害が起きるとどこに逃げるか決めておく。
地元意識を強く持つ。
自治会活動の活性化。
高齢になると自己主張を譲らず、頑固な人が多くて説得が難しい。
各自意識を持つことが大事。
自主防災会で資料の共有をしたい。
各地域の連携が大切。
3日間が自力で乗り越えられるような体制を考えておきたい。
家に家族が残った時1人で高齢者は移動できない。
近所の必要性を痛感した。
人間は面倒くさがり屋で楽観主義が合間って意識が低いので、意識を高めることが大変。